こんにちは。今回は知的障がい者の支援あるあるの一つ
『利用者視点でものごとを考える』ってどうしたらいいの?
に関しての記事になります。
結論から先に言ってしまうと、
【利用者の気持ち】と【自分(支援者)の気持ち】をしっかり分ける
ことが出来るようになれば利用者視点でものごとを考えられるようになるでしょう。
実例をもとに考え方と指導のコツを述べていきます。
『危ないのでやめましょう』は誰のため?
現場でよく聞く『危ないのでやめました』『事故になりそうなので中止にします』といった言葉。
これらは大抵、『支援者の意見』です。
怪我をさせたくない、事故の責任を取りたくない、発言者の意図は様々ですが、行き過ぎるとただの抑制です。
良かれと思っての行動であっても、利用者の意思が汲み取れていないなら支援にはなりません。
ではどういう風に考えて行けばいいのでしょうか?
『ヒビの入ったCDケース』は片づける?片づけない?
具体的に考えるため、実例(多少フェイク入ります)をもとに説明をしていきます。
Aさんの情報 ・知的障がい者施設に入所中。 ・音楽を聞くのが好きで、CDとCDケースを持ち歩いている。 ・ふらつきがあり歩行時は支援員が介助を行う。 ・簡単な2,3単語の会話が理解できる。 ・簡単な1,2単語で自身の意図を話せる。 ・痛みや怪我に対する反応は鈍い。
ある時、後輩支援員からこんなことを言われました。
『Aさんが持ち歩いていたCDケースにヒビが入っていたので、お部屋に片づけます』
その話を聞いた私は、
(Aさんは朝起きてから、着替えやご飯の時にもCDケースを持って歩いている。持つことを好んでいるんだろう)
と思いました。
そこでまず、『そのCDケースを持っていては駄目ですか?』と尋ねました。
後輩は、『ヒビが入ったCDケースでAさんが怪我をするかも知れない』と考え、片づけるという選択肢を取っています。
ですが『怪我をしないこと』を本当に望んでいるのは誰なのでしょうか。
Aさん自身が怪我をしたくない、と話したことはありません。そもそも、怪我の防止は支援員側の仕事なので、Aさんが改めて気にしないといけないような部分ではないのです。
なので『CDケースを持っていてほしくないのは支援員側』ということが出来るでしょう。
ではこの場合、後輩に対し『AさんはCDケースも好きだから、返してきてください』と話すのが正解なのでしょうか?
自分の意見もきちんと疑う
上で出た私の考えは
(Aさんは朝起きてから、着替えやご飯の時にもCDケースを持って歩いている。持つことを好んでいるんだろう)
というものでした。
果たしてこれは正しいのでしょうか?それに対してもきちんと疑い、自身の意図が入っていないかを確認します。
【着替えやご飯の時にもCDケースを持って歩いている】→事実
ですが、
【持つことを好んでいるんだろう】→個人の意見
となります。つまり『本当に持っていたいかどうかは、私にも後輩にもわからない』状態なのです。
これでは後輩も納得できませんし、利用者視点での支援や対応にはなりません。
指導する側はどうしても、自分の経験から自信をもってしまいがちです。
しかし『飛ばしていい基本』というのはありません。しっかり自身の意見も、細かく分けていく癖を付けた方がいいです。
というわけで、解決方法は次のようになります。
Aさんの意思を聞いてもらう
もっともシンプルかつ一番最初にやるべき事、でありながら、とても抜けがち。
この時私は、後輩に『Aさんに、どうしたいか聞いてみてください』と伝えました。
本人からの返答は『持ってる』とのこと。
その発言を踏まえて初めて、私の意見であった
【(CDケースを)持つことを好んでいるんだろう】が『事実かもしれない』と考えられるわけです。
怪我は防ぐに越したことは無いですがCDケースで大怪我を負う可能性は低いですし、
大怪我を負ったらその時には、他にも要因があることでしょう。
『たられば』を考えてばかりでは何もできなくなってしまいます。
まずは本人の意思を確認する事。
利用者視点でものごとを考える時の、出発点であり基本ですね。
繰り返し、実践することが大事
【利用者の気持ち】と【自分(支援者)の気持ち】を分けて考えるためには、
ひたすら繰り返し、延々と実践していくことが大事です。
『自分のための意見ではないか』と疑う心を強めに持ってみてもいいでしょう。
考え続けているうちにいつかできるようになるはずです。
身に着けてしまえばあらゆる場面で有用な考え方となるので、支援方法を組み立てる時に楽になるでしょう。
まとめ
- 【利用者の気持ち】と【自分(支援者)の気持ち】を分けて考える
くどいですが、基本でありとても大事なことなので繰り返します。
自分の価値観や意見と、利用者の意思は絶対に分けて考えましょう。
利用者の意思が推し量れない時もあると思いますが、
推し量れないから考えない、というのでは成長できません。
情報を集め、観察を続け、他の支援員と意見を交わした先に見えてくるものもあります。
飽きず諦めず続けてみてください。
ここまでお読みいただきありがとうございました。


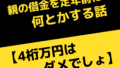
コメント